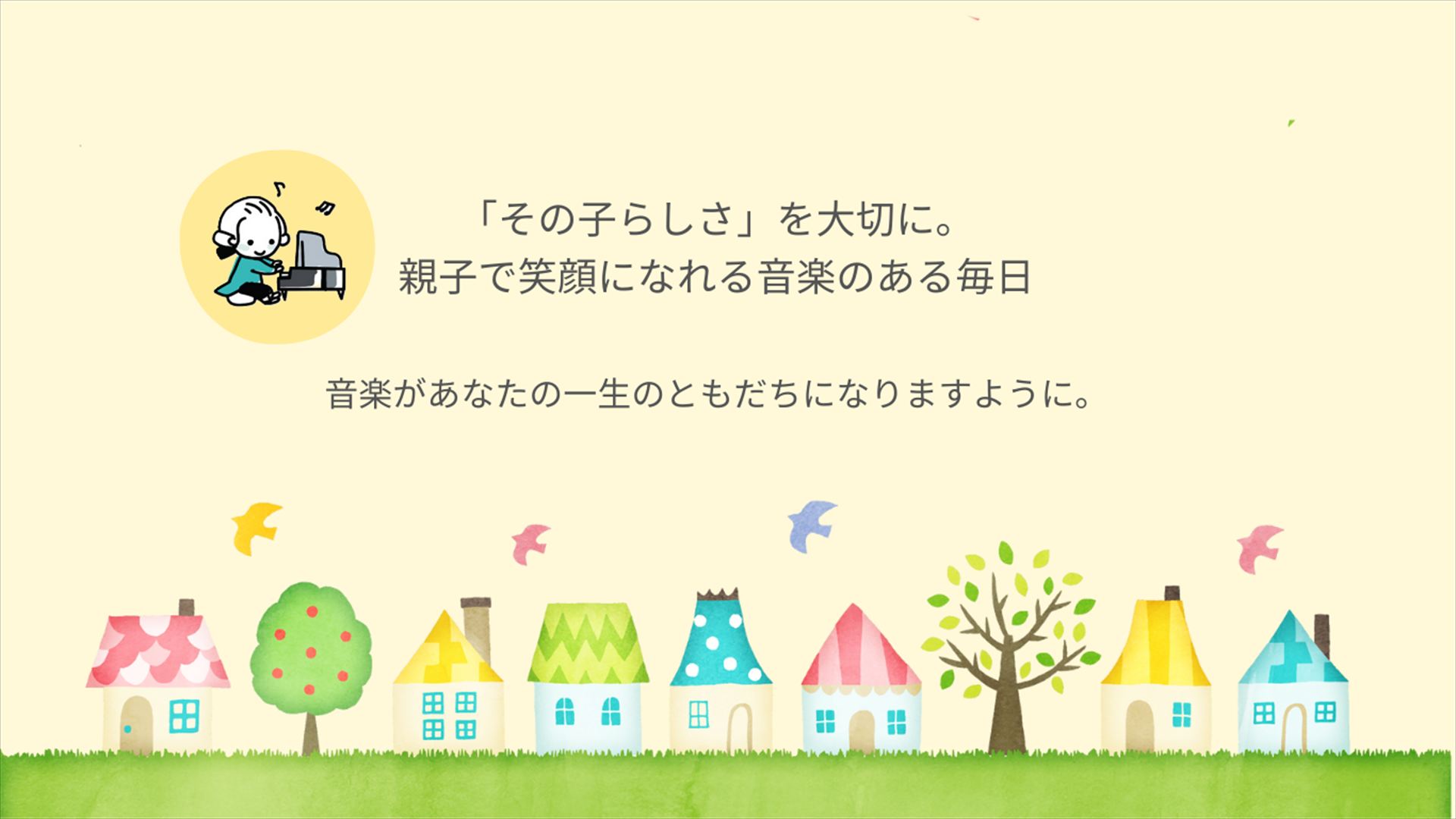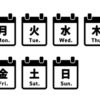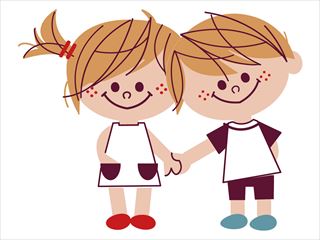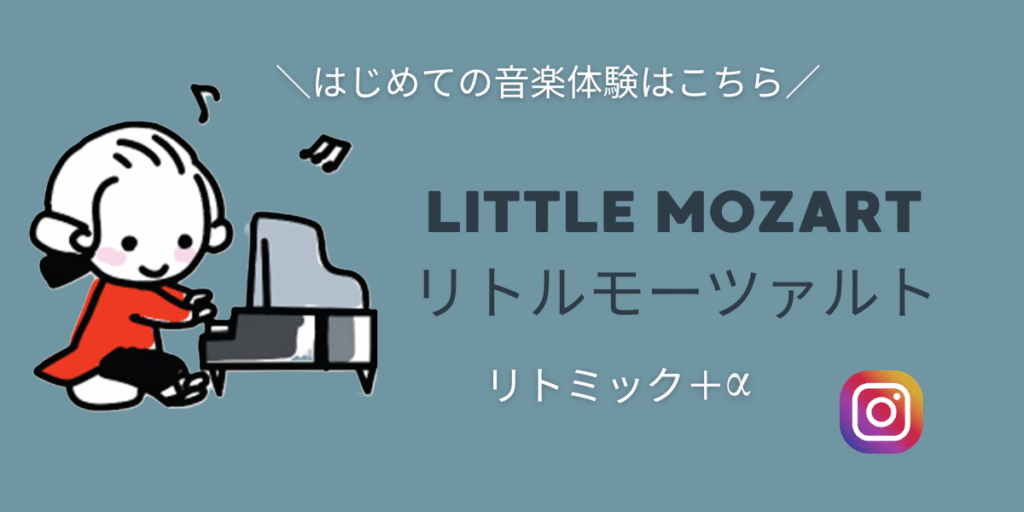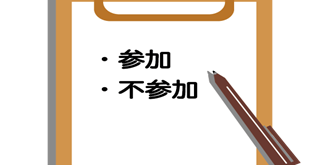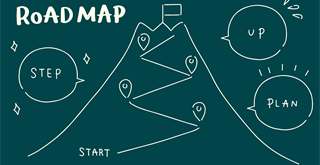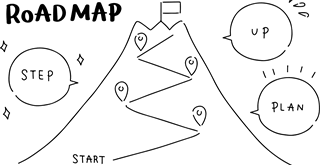5月リトルモーツアルト曲紹介 ビバルディ作曲【春】(四季より)
リトルモーツアルト曲紹介 ビバルディ作曲「春」~四季より~

ビバルディ作曲
春
「赤毛の司祭」は音楽家
アントニオ・ビバルディはバロック時代後期(17世紀ごろ)
イタリアで活躍した作曲家です
この頃「作曲家」という職業はなかったので
職業はローマ教会の司祭
兼、音楽教師やヴァイオリニストでした
「赤毛の司祭」と呼ばれていたそうです
欧米の人たちって
誰かを描写するとき
「髪の色は〇〇で、目の色は△△」
みたいに
表現することが多い気がします。
私も誕生日プレゼントに
「髪と目の色が黒だから」
といって黒いTシャツをもらったことがあります。
日本人からするとちょっと???かも
日本人大体黒だから…
色んな髪色の中でも特に
「赤毛」というのは
独特のイメージがあるんじゃないかと思います。
「赤毛のアン」
をご存じなら想像しやすいかも。
おしゃべりで、活発で、時には気性が激しい…なんて印象。
多分科学的な根拠をもとに言われていることではなくて
「A型は几帳面」とか
「B型はマイペース」みたいな、
血液型性格診断程度のことなのかな
(もっと真面目な話だったらすみません!)
もちろん
ビバルディ本人がそういう性格だったというわけじゃないんですけど
でも「赤毛の司祭」という異名は
日本人にはあまりピンとこないかもしれない
西洋文化のおもしろい一面だなと思います。
ハリーポッターの親友ロンとか
イギリスのヘンリー王子も赤毛ですね
話を戻します
バロック時代の作曲家といえば
ヨハン・セバスティアン・バッハが有名ですが
彼はビバルディを非常に尊敬していて
作品を研究して編曲をしたりしています
「標題音楽」のはじまり
学生時代、音楽の授業で学習した人が多いのではないかな
芦屋山手中学でもガッツリテストにでていました
楽曲を聴いてタイトルを答える問題とか
曲とソネットを結びつける問題とか
この曲の特徴は何と言っても
タイトルがついていること
「標題音楽」の先駆けです
それぞれ
春、夏、秋、冬
をテーマにした曲で
各曲には対応するソネット(14行詩)
が添えられています
このソネットには自然の描写や風景が表現されていて
ビバルディ本人が書いたともいわれています
このように
音楽と詩を連動させた構造は当時、画期的なことで
「聴く風景画」
と言われました
現代人が美化した(?)バロック時代
「春」は3つの楽章で出来ています。
第1楽章 春の到来、小鳥のさえずり
第2楽章 羊飼いのまどろみ
第3楽章 春の踊りと祝祭
というタイトル
今回演奏するのは第3楽章です
すごく平凡な感想ですが
300年以上前の作品でありながら
古さは感じさせない曲だと思います
自然の美しさ
季節の変化
人間の感情
など普遍的なテーマを扱っているからでしょうかね
個人的にこの曲の面白さを感じるのは
演奏アプローチによって印象が大きく変わること
クラシックファンの中で有名なのが
イ・ムジチ合奏団の演奏です
この合奏団の演奏は洗練された素晴らしい演奏なので
世界標準のようになっている感があります
一方
古楽器による演奏も近年盛んにされていて
全く違う印象で面白いです
古楽器によるアンサンブルの演奏では
ビバルディの生きていた時代の
楽器や演奏法を再現する
「歴史的演奏法」を採用しています。
何となくの印象でお話すると
前者はサラサラしていて優雅な響き
後者はエネルギッシュで粗削りな印象
もちろんどちらが正解ということではなく
好きな方を聴いて楽しめばよいのですけど
現代人が考える(ちょっと美化した)過去と
過去の人が表現する「今」
の違いなのかなとか…
こういう現象って音楽に限らず
あることなのかも
知らないことを美化するという
例えば
男性が思い描く
女子高の清楚で清らかな雰囲気と
実際
女子高の中で日々繰り広げられる
ちょっと粗雑な生活の違い…
とか
まあ、そういう雰囲気の違いです
この音楽が300年以上愛されてきたのは
言うまでもなく素晴らしい楽曲だから
なのですが
ちょっと陳腐というか軽薄な…
と感じるとすれば
現代の人たちが「美化」した
バロック時代の楽曲に
創り上げたから
という側面もあるのかなと思います
演奏によって印象のかわる
創造力をかきたてられる
面白い曲だなと思います