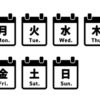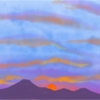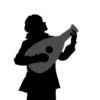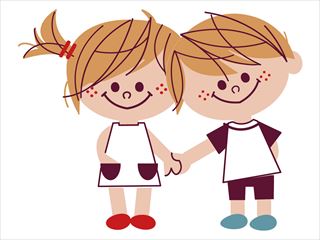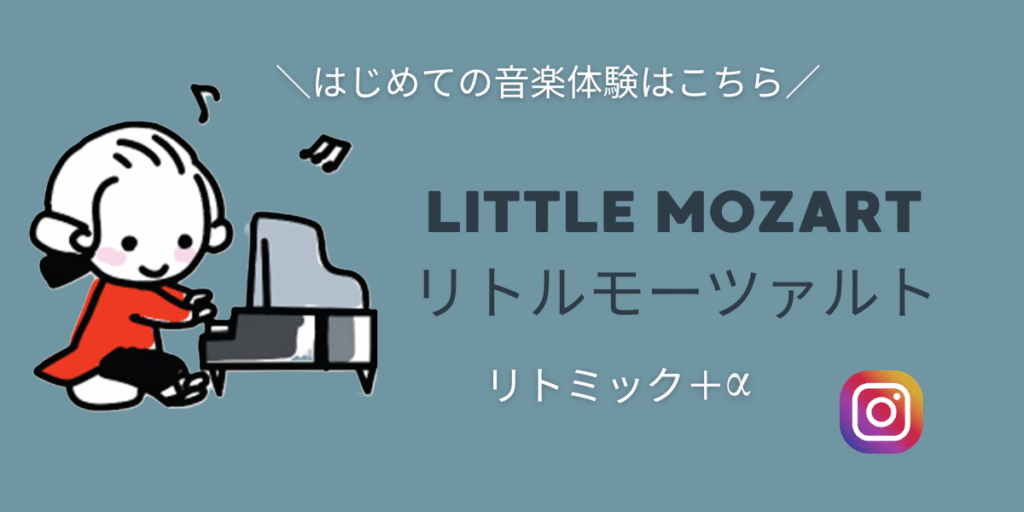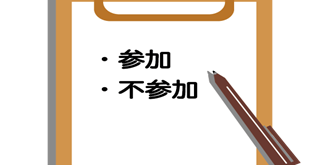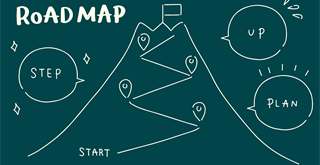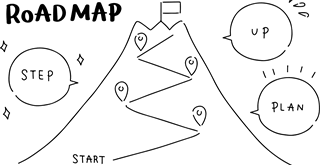文部省唱歌【かたつむり】ピアノ発表会演奏難易度別曲紹介 演奏難易度1
ピアノ発表会難易度別曲紹介
童謡【かたつむり】

短い歌の中に光る日本語の魅力
演奏難易度①
童謡
かたつむり
短くてシンプルな曲ですが…
「メリーさんのひつじ」や
「ロンドン橋」と同じ
付点のリズムが楽しい曲。
明治時代、文部省唱歌として発表された曲なのです。
作詞作曲は不詳。
口から口へと歌い継がれてきたのでしょう
文部省唱歌というのは西洋音楽の技法を取り入れることを
意図的に考えて選ばれた曲が中心なので
音楽的には西洋音楽で作られています。
けれども、歌詞がとても日本ぽいなと感じます。
「で~んでん む~しむし」の部分、
かたつむりのゆっくりした動きと言葉が絶妙に調和していて
雨に濡れた葉の上をのんびり動いている様子を想像してしまいます。
「かたつむり」というだけで、雨に濡れた葉を連想し
そのまま季節感に結び付くというのが、日本人の自然観なのかなと感じます。
「つのだせ やりだせ…」
とかたつむりに呼びかけているところも
自然や生き物との距離感が近い感じがします。
狂言「蝸牛」
この曲が音楽的にこの形になったのは明治時代ですが
歌詞は室町時代から伝えられたものです
というのも
日本の伝統芸能(歌舞伎などの楽しみ方について触れている記事あります)狂言の演目「蝸牛」で
主人公の太郎冠者(たろうかんじゃ)と山伏の男が
「でんでん むしむし でんでん むっしむし」
とうたっているから
まんま「かたつむり」の歌詞ですね
あらすじはここでは省きますが
狂言らしい
「なんやそれ!」
というしょーもない面白いお話です。
動画あったので貼っておきます
17分くらいから「でんでんむしむし」言ってます
重ね言葉の美しさ
「でんでん むしむし」
という表現
同じ音を重ねることで生まれるリズム感が楽しいですね
日本語の表現の特徴に
重ね言葉を使った擬音の豊かさがあります
「さらさら」
「ひらひら」
「ゆらゆら」
「ぺこぺこ」
「ぐずぐず」
「つれづれ」
「きらきら」
「しんしん」
「つくづく」
など
例えば
雨の降り方の表現だけでも
「しょぼしょぼ」
「しとしと」
「ぽつぽつ」
「ぽつりぽつり」
「ぱらぱら」
「ざあざあ」
上から順に雨の降り方が激しくなるのですけど
言葉の音が強くなっている気がします
Sしとしと
Pぽつぽつ
Bばらばら
Zざあざあ
どの言葉が最初に出来たのか分からないですけど
より強い発音、より弱い発音と
使いながら他の言葉との比較で作られたのでしょうね
日本人の言葉とか音に対する繊細さと表現力は圧倒的だと感じます。
パンダの名前
重ね言葉といえば
パンダの名まえって重ね言葉ですよね
カンカン
ランラン
古いか…
シャンシャン
タンタン
など
音を重ねるというのは中国から入ってきた文化なのでしょうね
英語でも重ね言葉が多いですけど
バイバイ
ママ
パパ
べべ
トントン
など割と幼児言葉の雰囲気なのかな…
あまり詳しくないのですが
ちょっと感覚が違う気がします
言葉の音やリズムで何かを表すのではなく
可愛らしさ、親しみやすさを感じるための使い方なのかな
こんなに小さな童謡からでも
感じられることって多くて面白いです
小さな生き物への愛情
自然との近い距離感
そして室町時代からつづく日本人の繊細な言葉に対する感性など
簡単で親しみやすい音楽に凝縮されているから素敵です
大切に歌い継いでいきたいものです
最近の日本は熱帯地方のような気候で
雨の降り方に情緒がありませんから
そのうちこういうしっとりした湿度の感じは
伝わりにくくなるのかもしれませんけどね