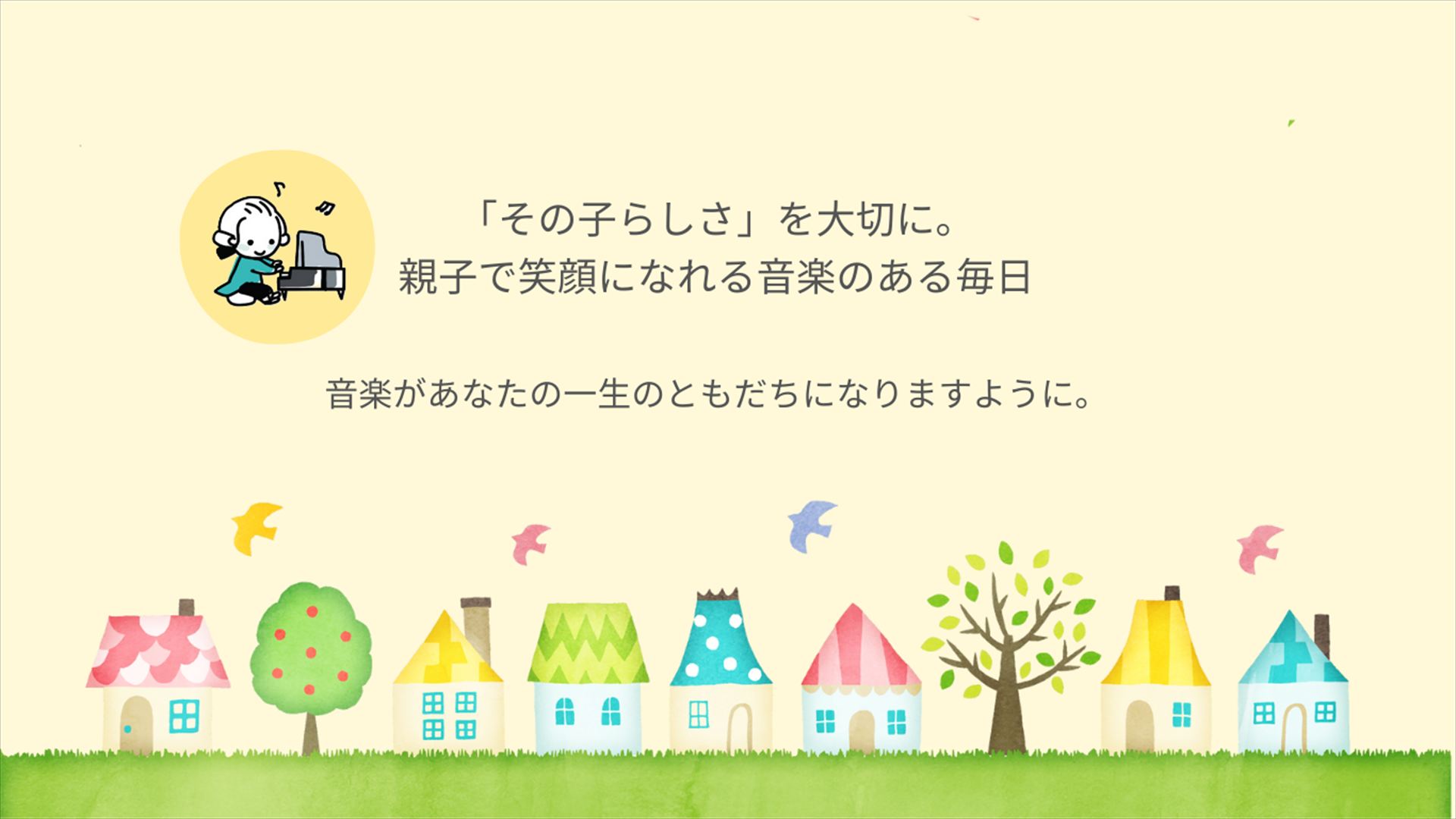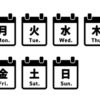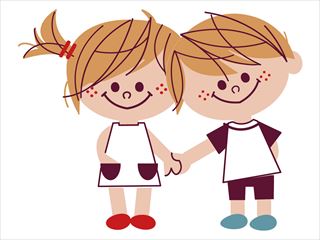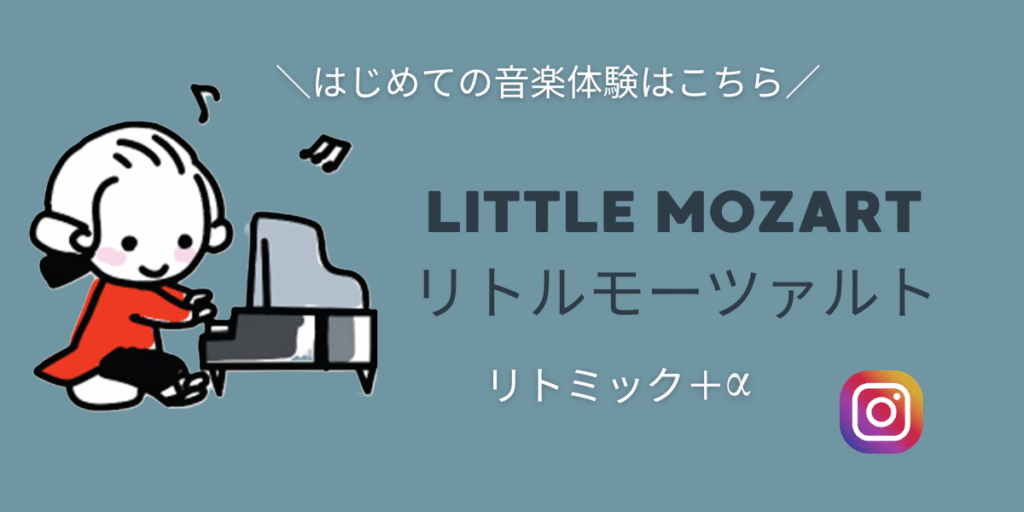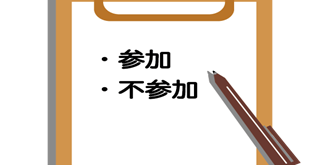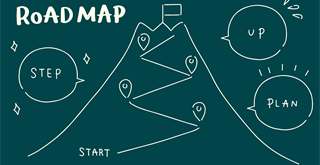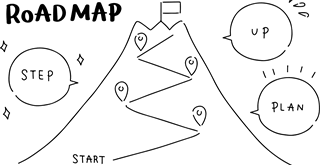ピアノを続けるための環境づくり~気合、根性、やる気をアテにしないで!
ずっとピアノを続けるために必要なこと

ピアノのレッスンをはじめる時に
保護者の皆さんがおっしゃること、
ほぼ100%共通していることがあります。
「音楽を好きになってほしい。
そして生涯音楽を楽しんでほしい。」
という想いです。
そして
出来れば子ども達には
楽しい気持ちで取り組んでほしい
という想いもお持ちの保護者が多いです。
ご自身が子どもの頃、
ピアノの練習が苦痛だったり、
先生が怖かったり、
親に「練習しなさい!」とガミガミ言われたり。
そんな経験をお持ちの方も多いかな…
それでも続けていて良かったと思う方もいれば、
辞めてしまったことを後悔している方もいます。
どちらにしても、
我慢や根性で続けることの限界を
身をもって知っている保護者が多いのは今の保護者のみなさんの世代の特徴でしょうかね。
さて、
では、「続けるために何が必要か」
これが一番大切な問題ですよね。
まず不正解は
気合・根性・我慢
ほぼ続きません…
「やる気」に頼ってもだめです
正解は
続けられる環境を整えること。
大人が上手に「術中にはめる」とでもいいましょうか
前回はご家族を巻き込みましょう!というお話しました。
今回は「仲間がいることのアドバンテージ」についてお話しします。
発表会は再会の場所
今回の発表会でも何組か演奏していましたが
普段はピアノの演奏から遠ざかっているけれども
発表会の連弾には出演する子どもたちが
毎回何組かいます。
例えば、小学校高学年でピアノを辞めてしまった子が
中学生の従姉妹と一緒に連弾で参加したケース。
普段は部活動や勉強で忙しく
ピアノに触れる機会はほとんどありません。
でも
年に一度のこの機会のために
久しぶりにピアノの前に座るのです。
最初は指がうまく動かず
楽譜を読むのにも時間がかかります。
でも、
連弾相手と一緒に好きな曲を選び
それぞれが自宅で練習し
限られた回数の合わせ練習を重ねていくうちに
何かが蘇ってきます。
「やっぱりピアノって楽しい」
「音楽っていいな」
この瞬間が、 私が大切にしたい体験なのです。
人生は長いんだから、のんびりいこう
長い人生でピアノにガッツリ向き合える時間は、 実はそれほど多くないでしょう。
小学生の頃は毎日練習していても、
中学・高校では部活動や受験勉強、
大学生になれば就職活動、
そして社会人になれば仕事や家庭。
でも、それでいいのです。
普通のこと
大切なのは、
ふと思い出してピアノを弾いたとき、
「やっぱり楽しい」
と感じられること。
指は昔ほど動かないかもしれません。
楽譜を読むスピードも落ちているかもしれません。
それでも、
鍵盤に触れたときに心が躍る感覚があれば、
それは音楽が「一生の友」になっている証拠です。
いろんな連弾仲間たち
連弾仲間は本当に様々な形があります。
兄弟姉妹同士、
いとこ同士、
おじいちゃん、おばあちゃんとの世代を超えた連弾。
同じクラスの友だち、
近所の子どもたち、
習い事仲間。
グループレッスンの仲間(幼なじみといっていいかも)
発表会で出会った他の生徒、
年齢の違う生徒同士のペアリング。
どの組み合わせも、それぞれ独特の魅力があります。
年齢が近い同士なら共通の話題で盛り上がり、
年齢差があれば互いに学び合う関係が生まれます。
なんというか・・・ 音楽って不思議ですよね。
年齢も性格も全然違う人同士が、 一つの曲を通じて心を通わせることができるんです。
連弾がもたらす特別な学び
一人での演奏と連弾では、 全く違うスキルが求められます。
連弾では、 相手の音を聞きながら自分の音をコントロールする必要があります。
テンポを合わせ、
音量のバランスを考え、
時には相手をリードし、
時には相手に合わせる。
音楽的な技術だけでなく、 協調性やコミュニケーション能力も育てます。
何より、
「一人では奏でられない豊かな音楽」
を作り上げる喜びは連弾ならではの特別な体験です。
気合・根性・我慢より大切なこと
「最近うちの子、やる気がなくて練習しないなあ」
と感じたことのある保護者の皆さん
要注意です。
しつこいですが
気合、根性、我慢そしてやる気
これらはピアノを続ける原動力になりません
無理です(たぶん)
すぐに限界がきます
そんなもの当てにしないで
子どもがピアノを続けられる「環境づくり」にまい進してください
具体的なことは
こちらをご覧いただくとして・・・
(また追加記事も書きますね)
ピアノを続ける環境づくり
そのために手堅い方法は
仲間をつくることです
保護者のみなさんが仲間になるもよし
お友だちや親戚関係を探すもよし
ぴあぴあの中で仲間を探すもよし
子ども達が将来
「ピアノを習っていて本当に良かった」
そう心から思えるように、
環境づくりについて
ときどき考えてみてくださいね