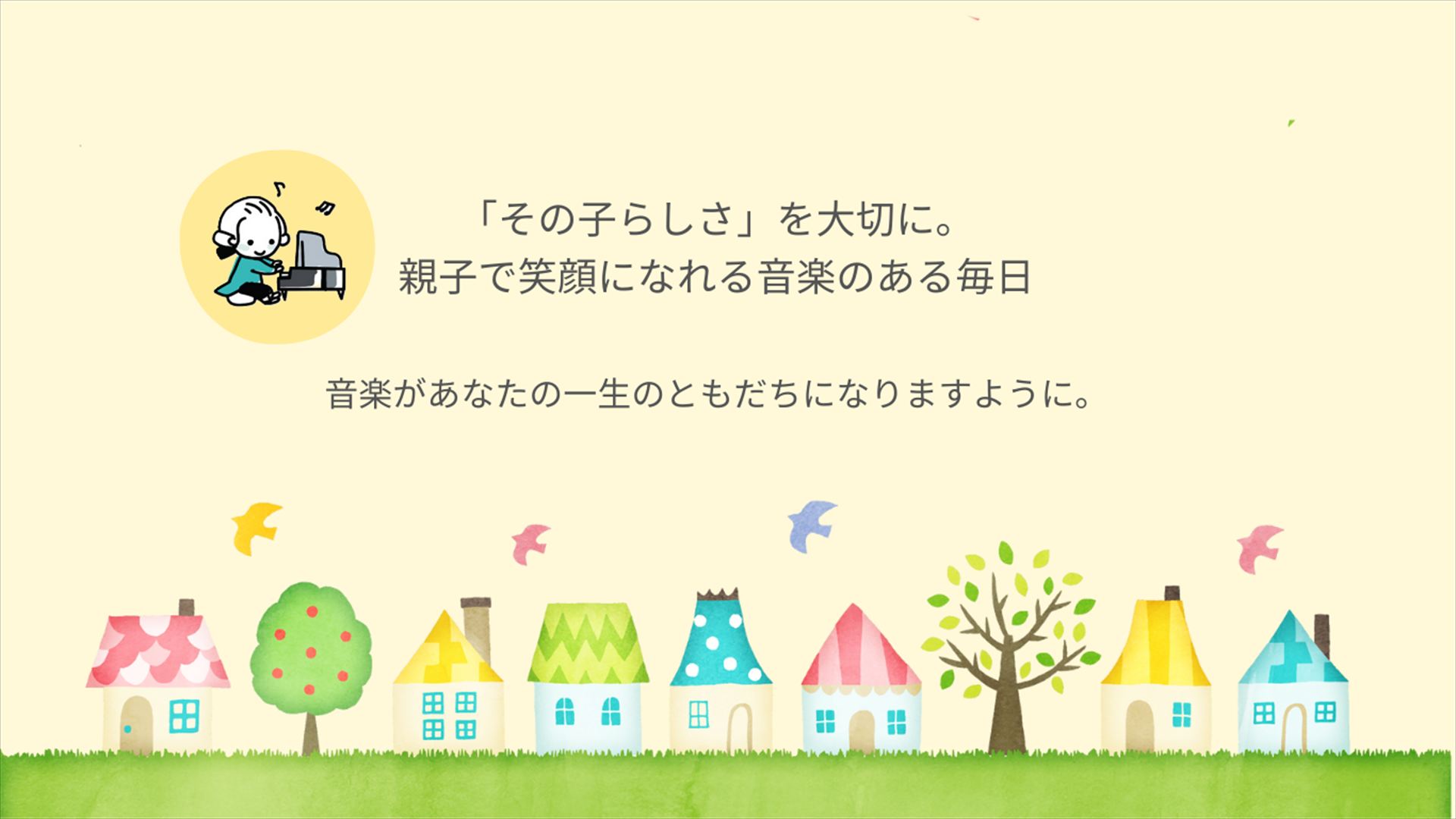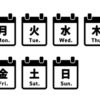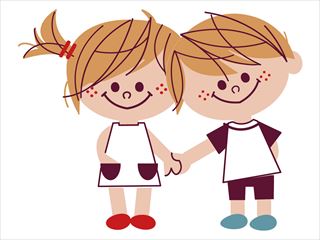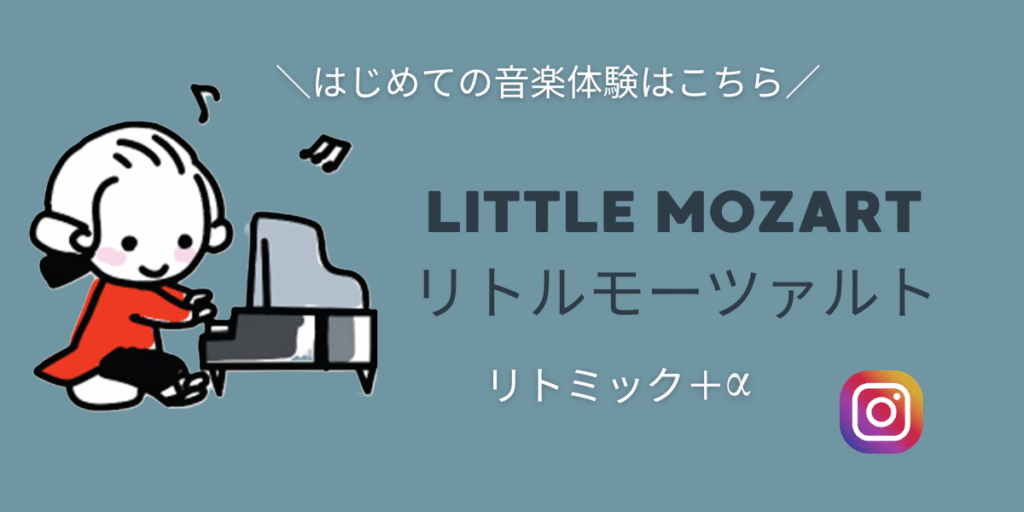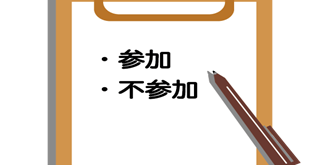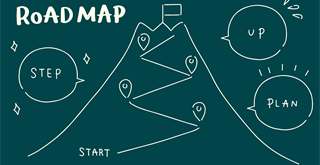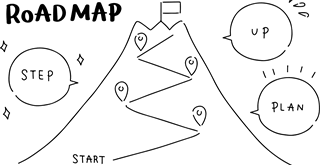「理系脳」の育て方=論理的思考力ってことなのかな(たぶん)
「理系脳」を育てるのに音楽が有効?
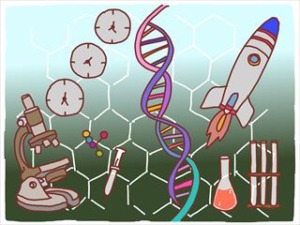
「理系」「文系」という選択を考えたことがある人は多いと思います。
「理系脳」なんて言葉も聞きます。
世の中のトレンドとして、子どもを「理系脳」にしたい親が多いようです
なぜでしょうね。
学生時代、数学で苦労したからでしょうか
就職に有利っぽいからでしょうか
私は「芸術系」だったので蚊帳の外でしたけどね。
ちなみに
夫は「体育系」だったので同じく蚊帳の外。
両親そろって副教科!
だからうちの子どもたちは
親からは有益なアドバイスはもらえない代わりに
何のプレッシャーもないという
恵まれているんだか
恵まれていないんだか
・・・という環境で育ちました。
そして勝手に理系、文系、好きな方に進んでいきました。
そんな「芸術系」の私ですが、永年ピアノを教えていると
「音楽をしている子は、算数(数学)が得意になるの?」
というご質問を割とよく受けます。
「東大生が子どもの頃やっていた習いごとはピアノって本当?」
と同じくらいよく受けるご質問です。
こちらについては過去に記事で書いているので
よかったらどうぞ
結論から言うと
ピアノを習えば算数の点数が良くなるというのは違うと思います
普通に計算ドリルやってる方がいい点が取れます
ただし
全く関係ないとは言えないけど…といったところ
イコールで結べる単純な話ではない・・・
因果関係ではなく相関関係はある気がします
ただし順番が逆ですけど
つまり
数学的思考が得意な子どもは
音楽の論理的な部分が腑に落ちるということ
音楽の論理的な構造や楽曲の解釈といった面を
数学が好きな子どもは
「あ、そういうことか」
とすんなり理解します
数式とかそういうことではなくて
音楽を「感情」ではなく
「理性」で考えることに面白さを感じるとでもいうのかな
音楽と数学と天文学
音楽と数学は歴史をさかのぼれば源流が同じ
もともと兄弟のようなものでした
古代ギリシャでは、音楽、数学、天文学は
同じ学問として教えられていました
「調和の学」
として宇宙の秩序を理解するための手段だったのです
宇宙の秩序!?
笑ってしまいますか?
壮大なスケールの学問なんですよ
だから
音楽が単なる
「理系脳を作る道具」
として考えられる・・・としたら
心外というか、ちょっと残念な感じがします
数学と同じ構造を持つ、もうひとつの言語
私の感覚では
音楽と数学は同じ構造をもつ言語
といったところ。
音楽というと、耳で聴くものですが
楽譜を開いてみると
それは、緻密に設計された
「数式」とか
「プログラミング言語」
に近いものだという感覚があります
- 縦軸=音の高さ
- 横軸=時間の流れ
- リズム=時間の分割
- 和音=数比の調和
楽譜は視覚化された数学構造といったところ
ピアノを弾くときは
構造を目で読み
指をコントロールして
脳で予測しながら
進めます
指を動かす前に
次の音
和声の流れ
曲の構造が頭の中に描かれます
音符をひとつずつ追うのではなく
パターン全体を図形的に
捉えて演奏する
これって
図形問題
空間認知
と同じプロセスではないのかな
と思ったりします。
音階は数学から生まれた
「ドレミファソラシド」は
長い歴史の中で数学的研究に裏打ちされた体系です
音階は美しく聴こえる比率(整数比)でできており
鍵盤の距離感は数と長さの対応になっています
このあたりのことも過去に記事を書いていますので
よかったらこちらの記事をどうぞ
楽譜を読んでピアノを弾くということは
数という抽象と鍵盤を弾くという具体を
行ったり来たりしています
数学が好きな子どもは
こういう抽象的な話を面白がって聴きますし
「ドレミファソ」がどうやってできたのかというような
数学的な話を感覚的に理解します。
無駄なことはない、これさえやれば安心なこともない
子もの教育というのは
1+1=2
のような単純なことではありません
音楽をやれば数学ができる
数学ができれば音楽ができる
そんな単純な話はありません。
子どもは、
少しずつ色々なものの影響を受けながら育ちます。
小さなピースを集めて
モザイク画を作るように育つのです
無駄なものはひとつもないし
これさえやれば良いというものもありません
音楽も、数学も、遊びも、読書も
すべてが子どもの中で響き合い
やがて
その子らしい思考や感性を形作っていくのです。
幼児期は「経験」を集める時期
小学校にあがる前の子どもたちは
世界をそのまま丸ごと吸収する時期です。
机に向かって数を学ぶよりも
心と身体を使って
五感を全て使って
ただひたすら
多種多様なことを感じる時期ということです
多種多様な曲に触れる
多種多様な音に触れる
自分で音をだしてみる
自分の身体を使って多様な楽器を触る
こうした体験をたくさんすること
それが
将来の抽象思考の土台になるかもしれません
なるかもしれないし
ならないかもしれない
それでいいんじゃないですかね。
それが思考力をあまり育てなかったとしても
ピアノは上手に弾けるようになりますから
音楽は「知性のはじまり」
音楽は、感性と知性を育てる複合的な学びです
ひとつの曲を通して
人の感情に想い巡らせたり
歴史、文化、地理的なことも考えます
数学的思考、論理的思考は
その中のひとつにすぎません
幼児期の子どもたちが
音にワクワクし
耳をすませ
リズムを感じる
そういった瞬間
何かが育ち始めているのは確かです
それが「数学」という形で表れるかはわかりません
でも音楽を通して触れた
構造
パターン
論理
調和
そういったことは
確実にその子の中に蓄積されていきます。
音楽教育は
算数の点数を上げるためのものではありませんが
世界を色んな方向から理解するための方法を
子どもに手渡すことはできます
どんな花を咲かせるかは、誰にもわかりません
けれども
無駄なピースはひとつもないのです。